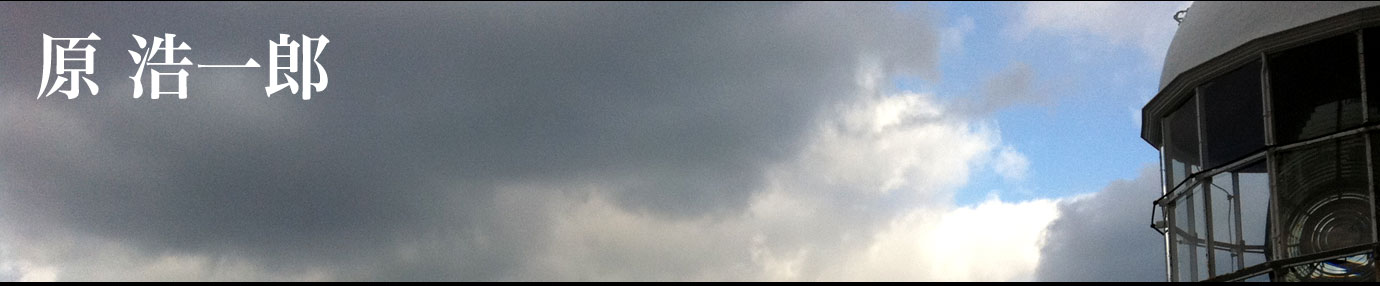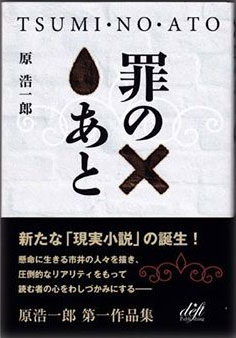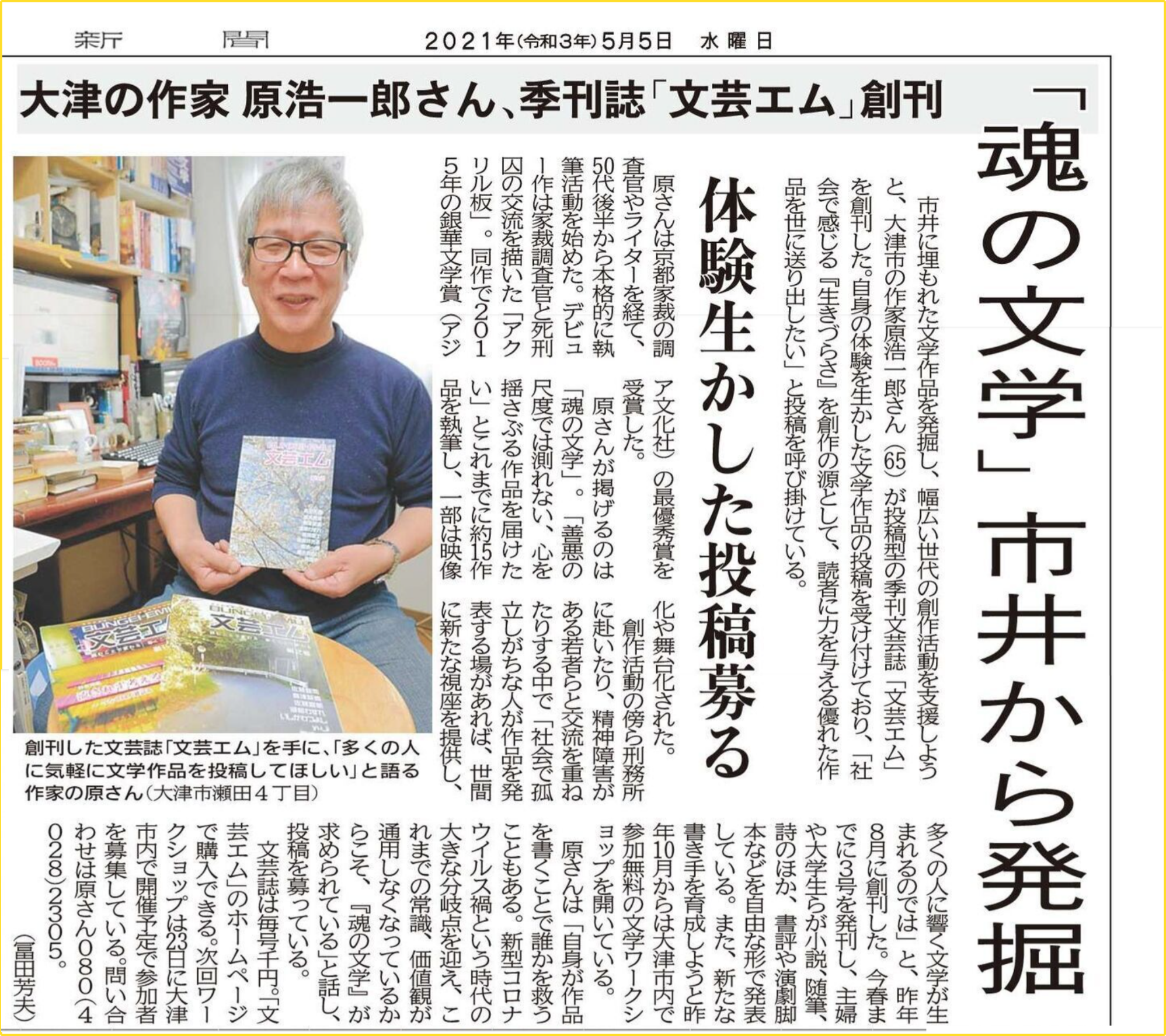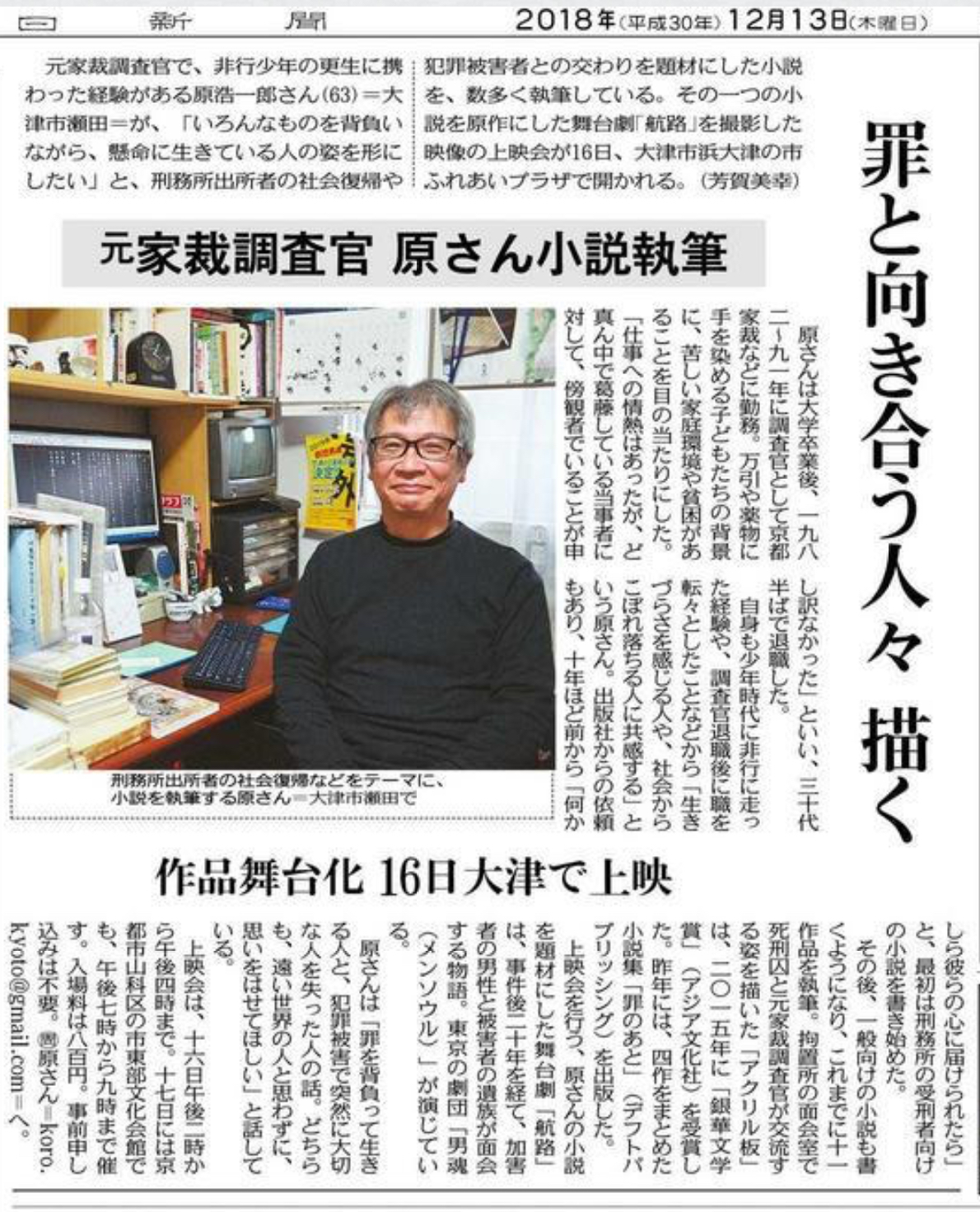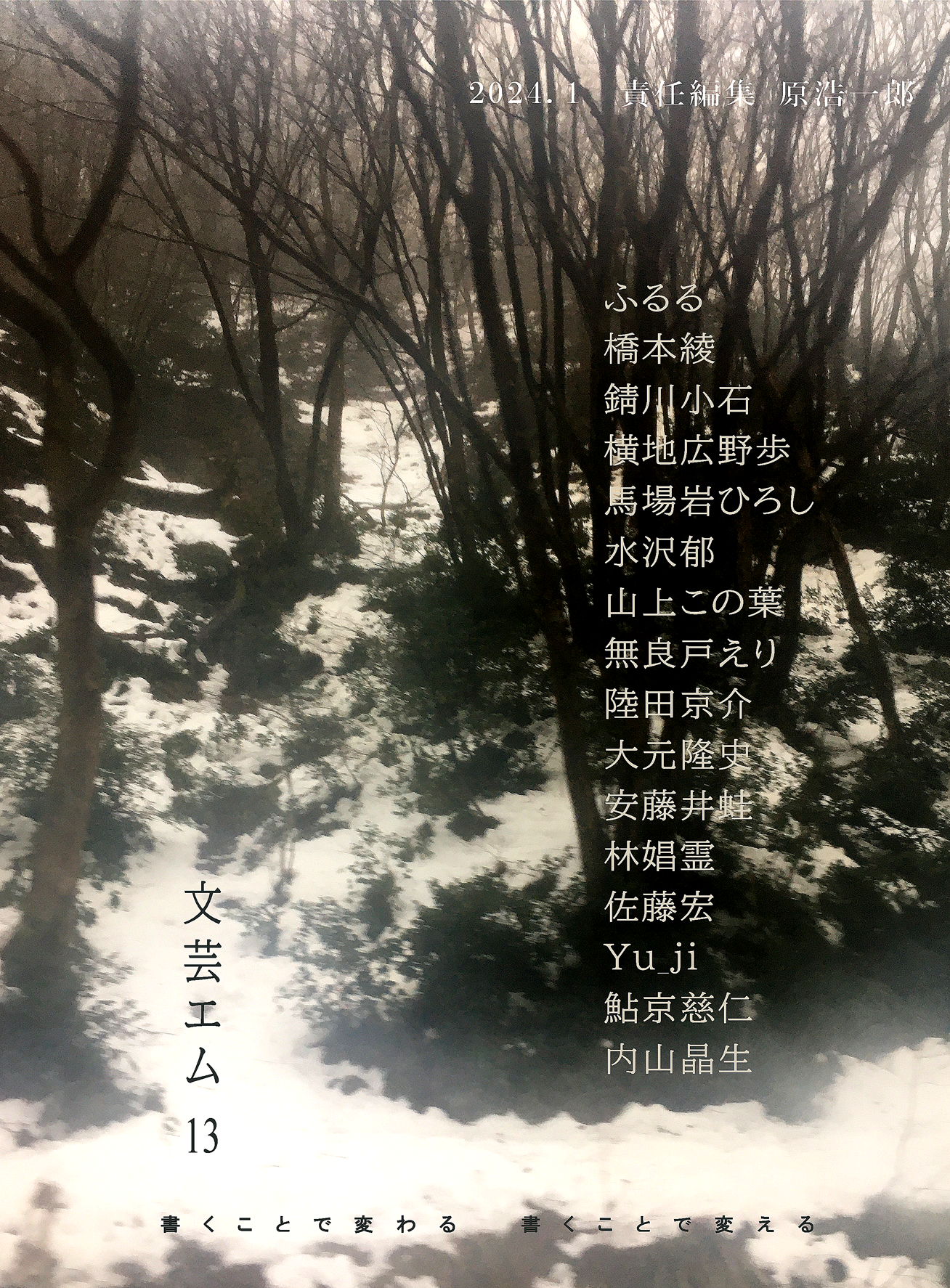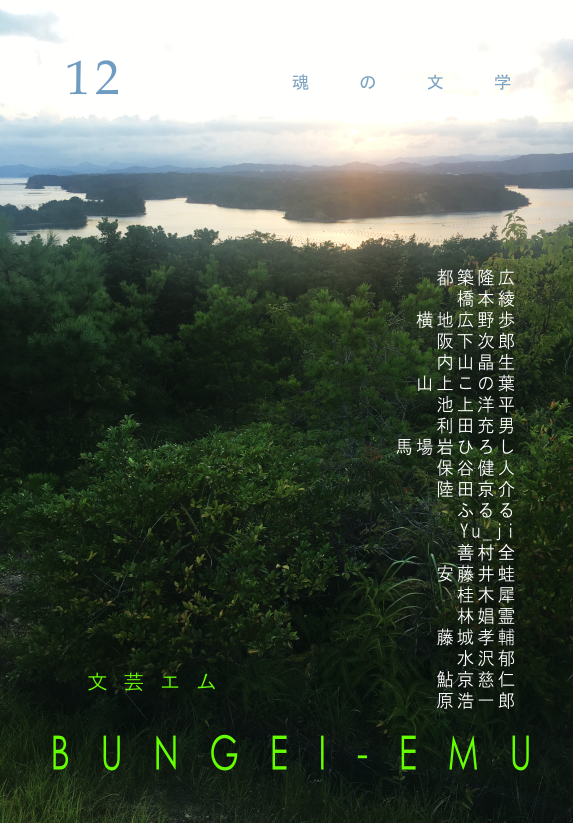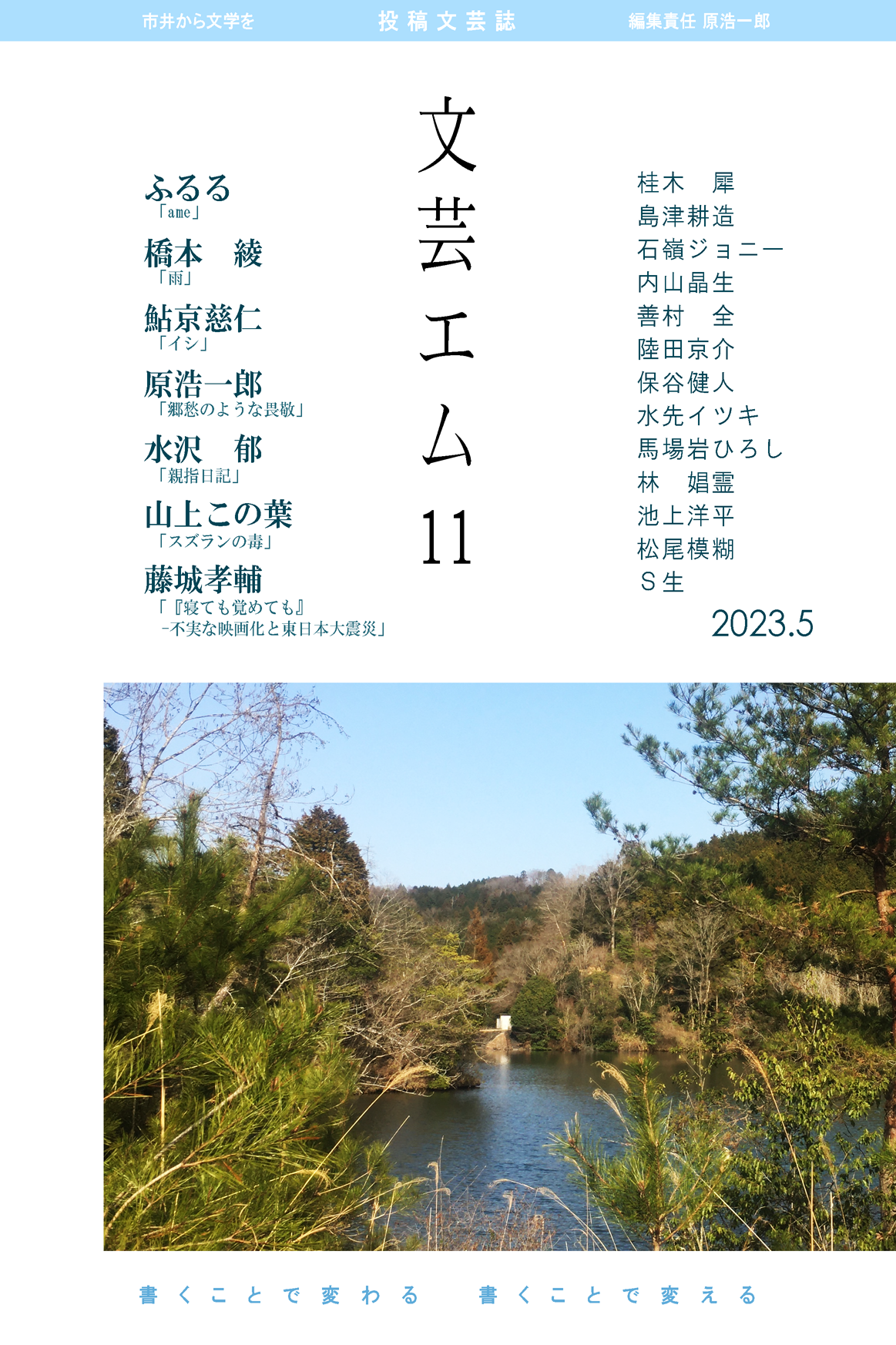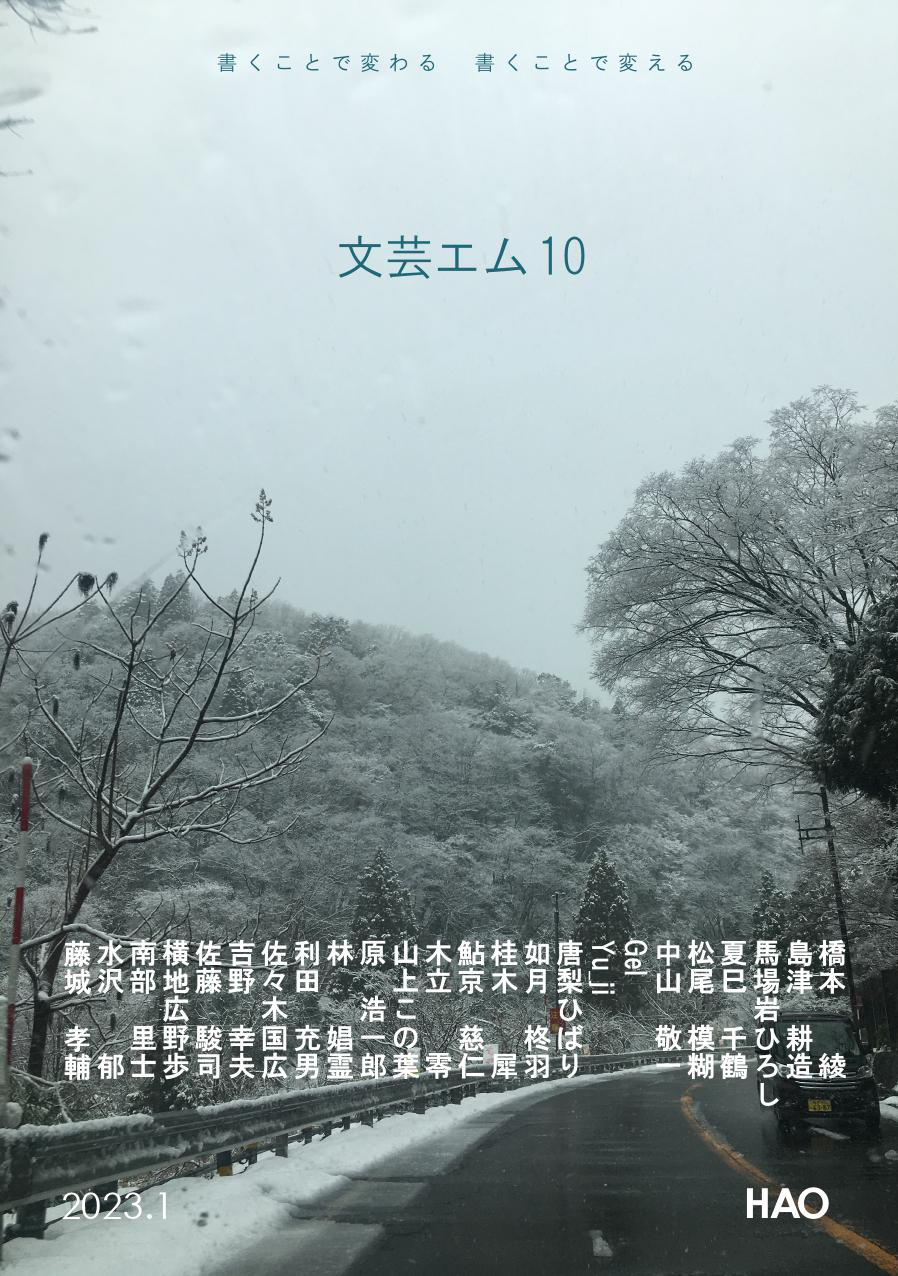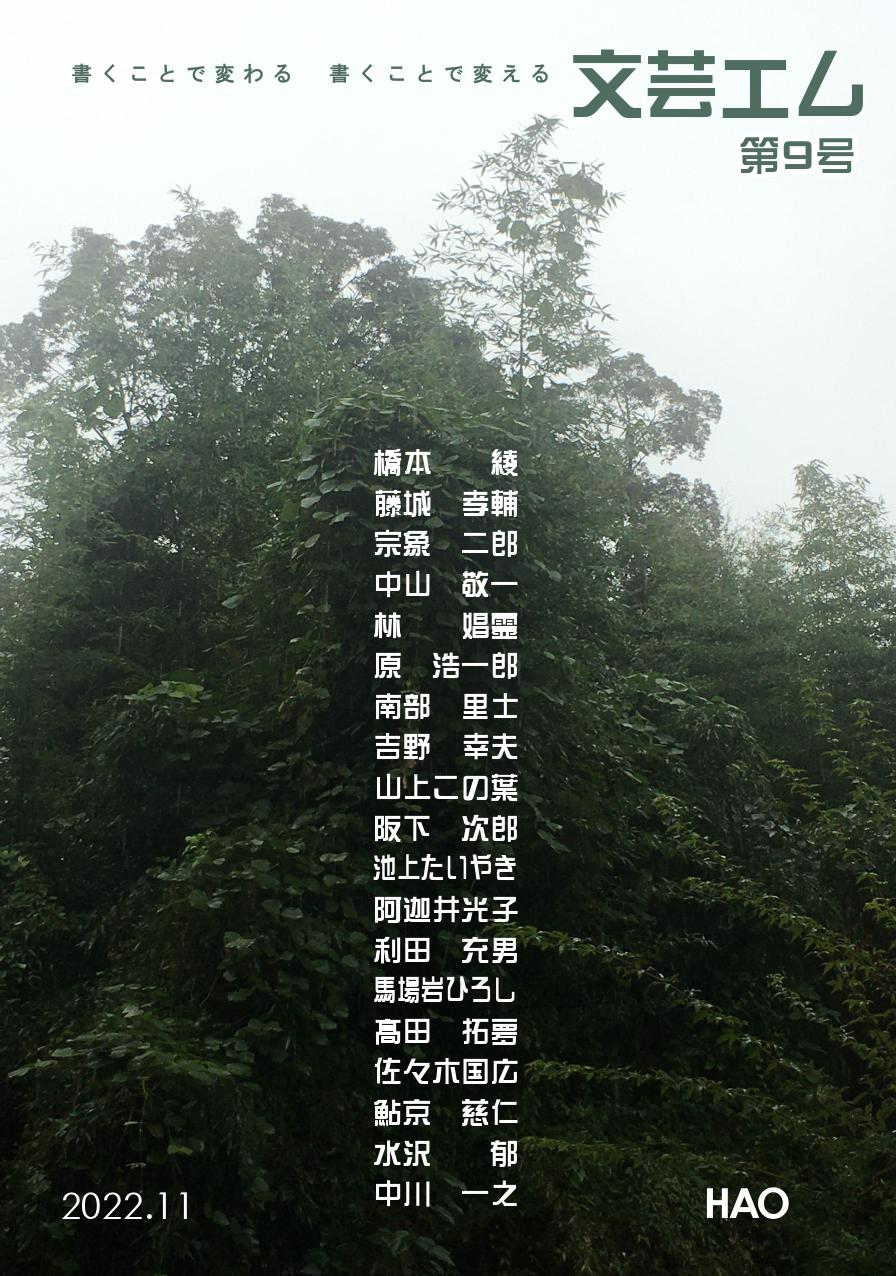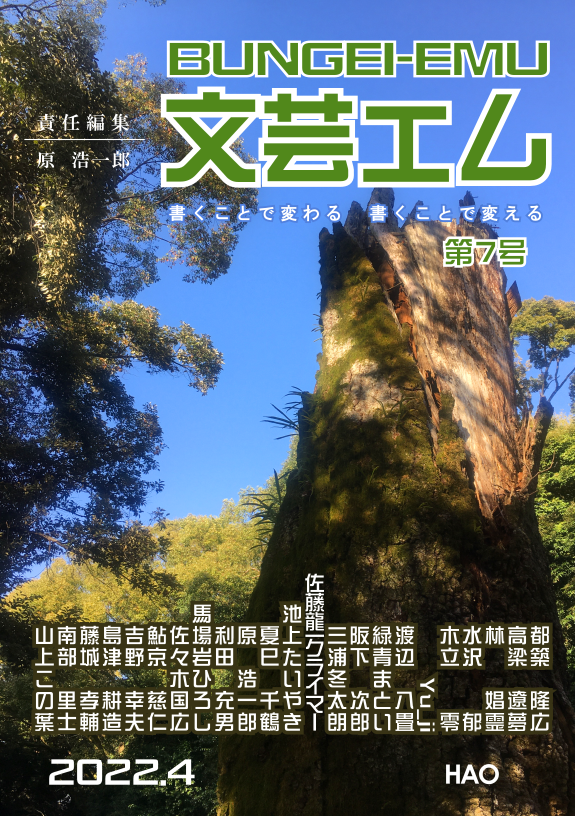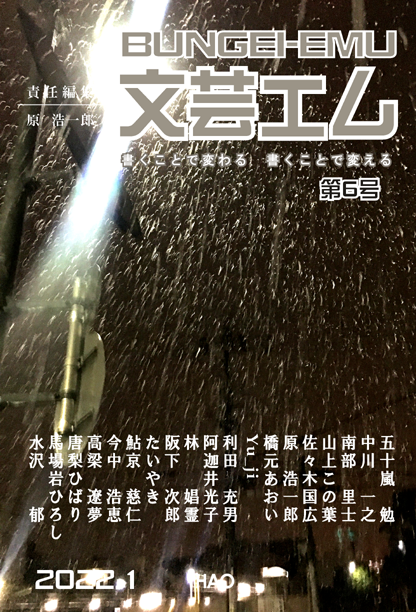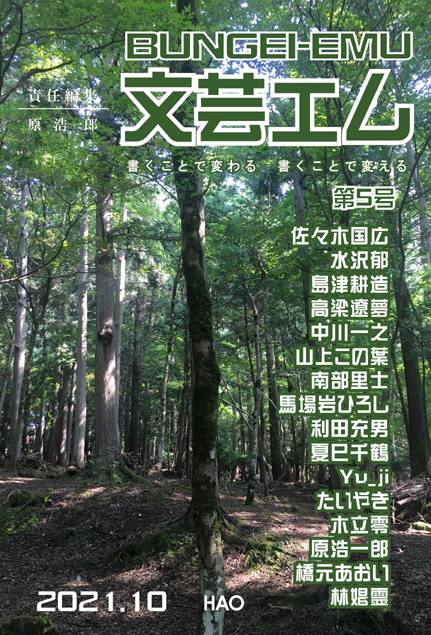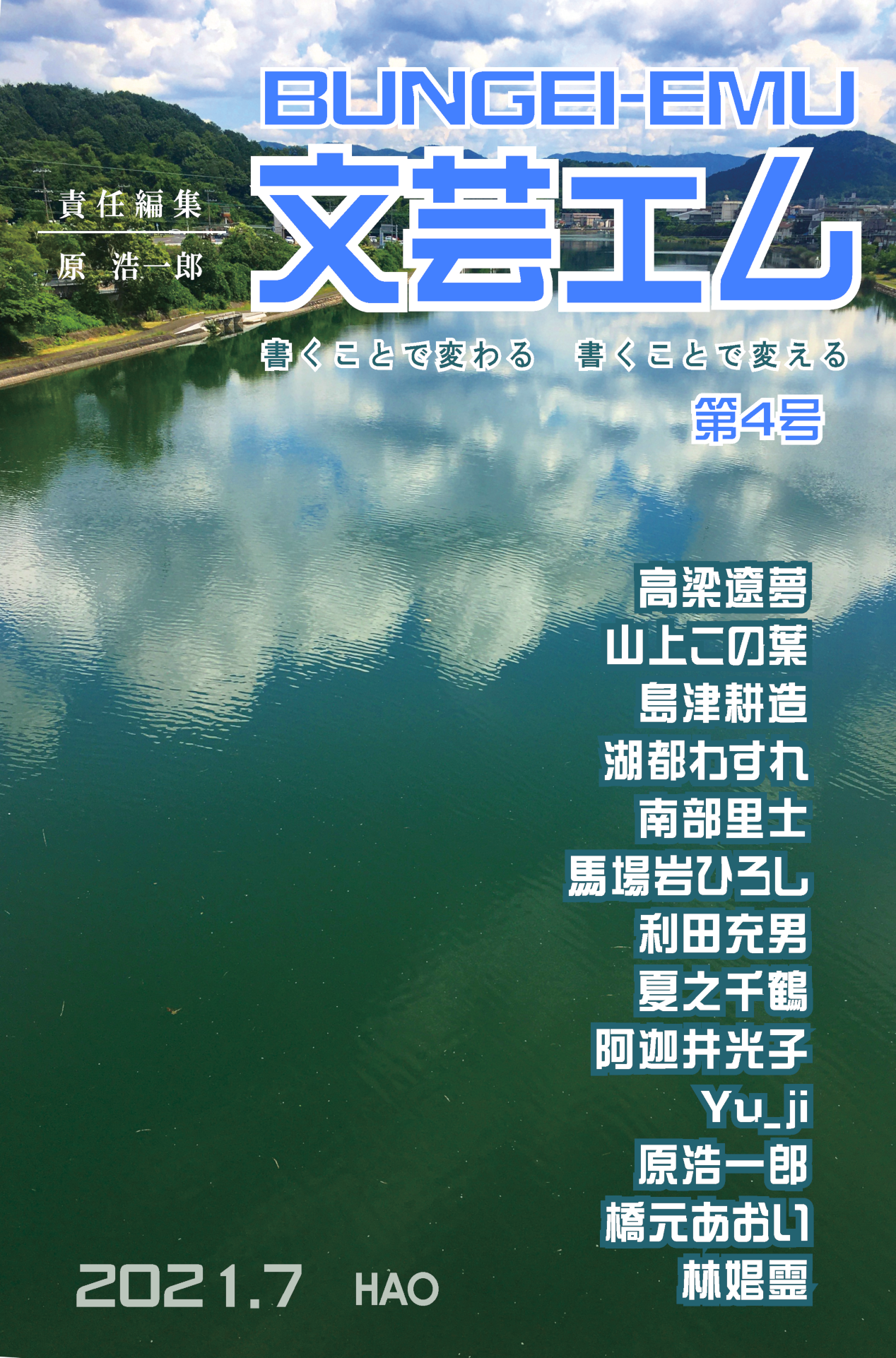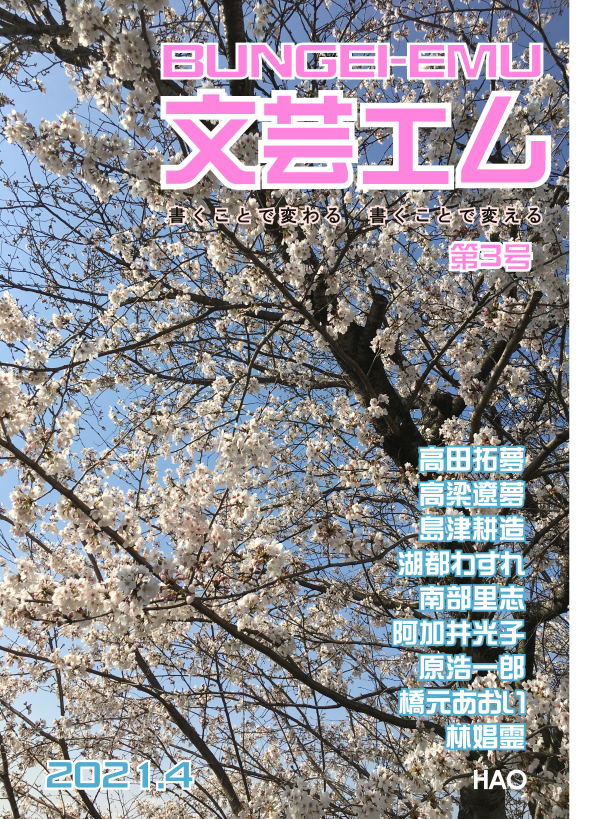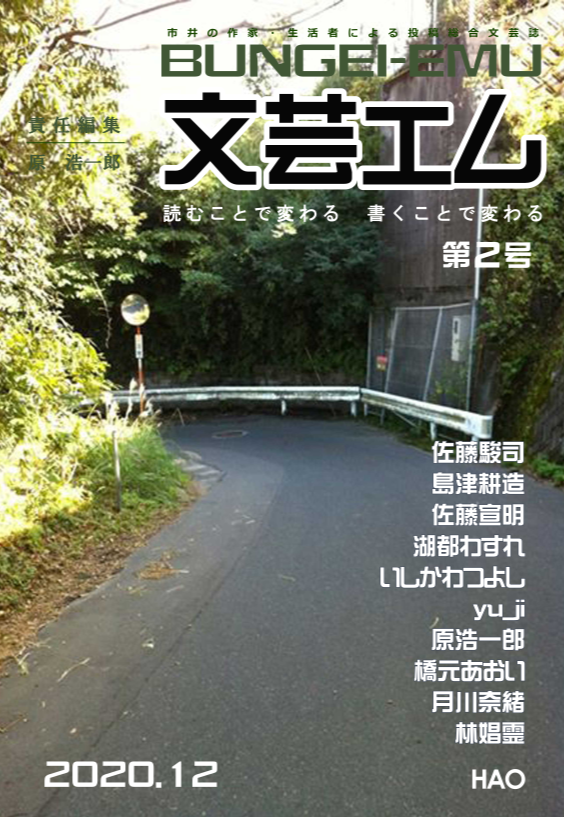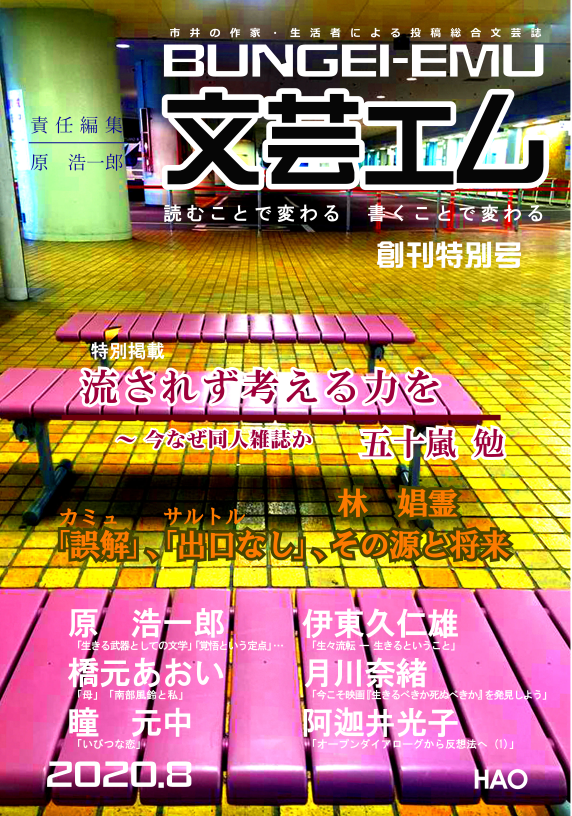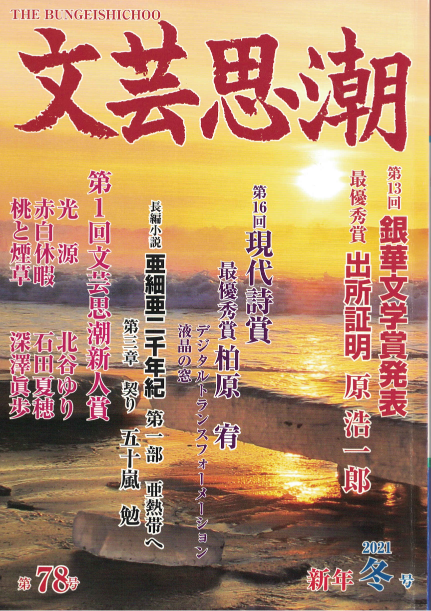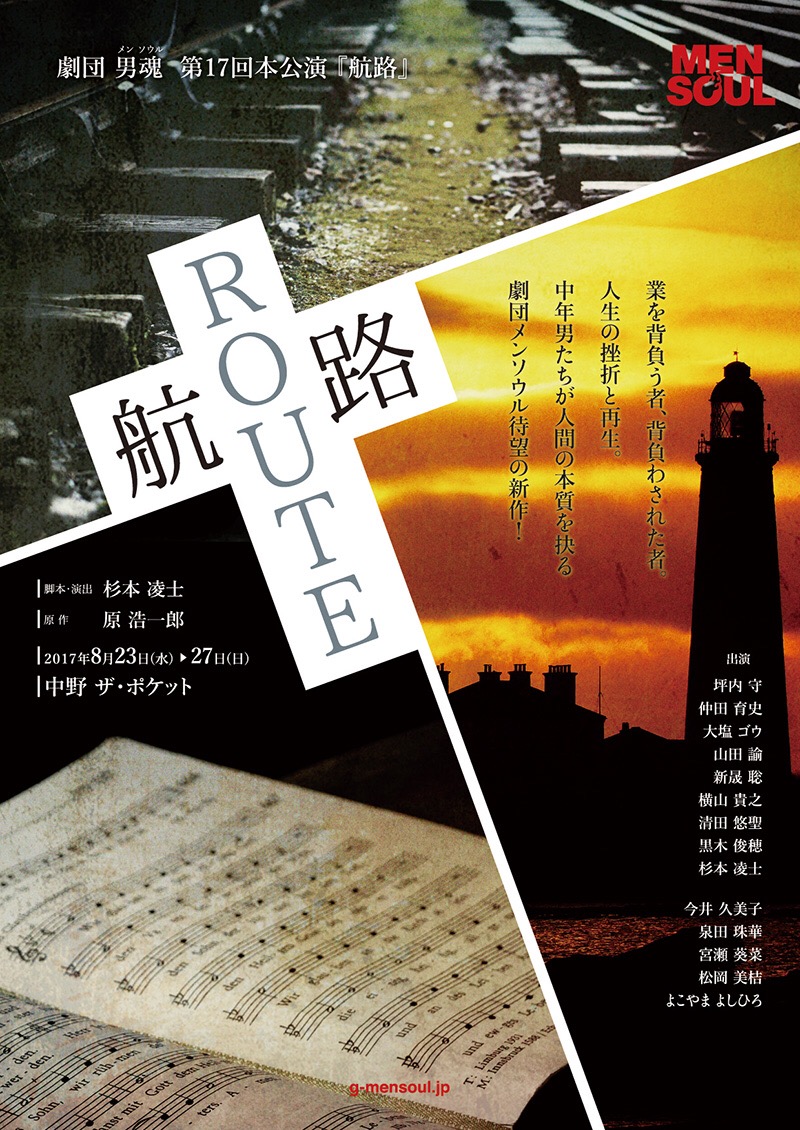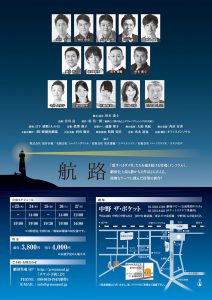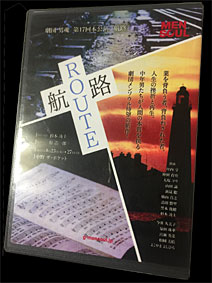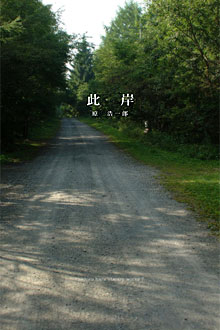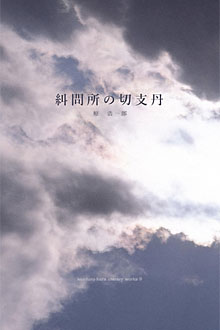「割木を書く」(中川一之 『文芸たまゆら』129号)
人間は自分に都合のよいナラティブによって自分を保っている。それは非難されるべきことでもない。
だから一人称の語りはあてにならないことを逆手にとって、信頼できない語り手と暗黙に示すことで、作者は書くことによってでなしに、書かないことによってもうひとつのストーリーを浮かび上がらせることもできる。
ただそれは真実と虚構を対置するものというよりも、それぞれの「歪曲した真実」が交錯して出現する世界であろうし、またそうしたそれぞれのナラティブの迫真性に嘘はないこともこの世界の妙である。
いずれにしても、真実を測る万能のスケールとして信頼できる語り手を措定してそれに一切委ねることについて、様々評価はあろうと思う。
ここで描かれた「虐待」は被害者である「私」にとっての事実であり、それ以上でも以下でもない。小説では最後、父の意外な言葉を私は目にする。それはただのテキストであり、父にとってどのような意味合いで発せられたかについては、死に向かう病床で書かれたらしいこと以外、その背景や事情、心情や意図は不明であり、もはや確かめようがない。むしろ、それを目にした「私」がどのように受け止めるかと鋭く問われているところで、小説は閉じられている。
これは許しを請う加害者に対する、被害者の許しがテーマだろうか。或いは人の善性は虐待を重ねた肉親においても否定されず宿っているのだと読者の期待に安堵を与えるものなのだろうか。私には父が記したテキストが暴き出す「私」の父に対する心情と態度こそにただ興味は惹かれる。そこで「私」のナラティブは変容するのだろうか。「私」はそこでようやく父にではなく、「私」に向き合うことを強いられることを小説の作者はよく承知している。
いわゆる大文字山の大文字焼を遠景の叙情としてでなく、具体的に近接した言わば当事者として体験する内情が突きつけるのも、ふんわりとした印象ではなく内からの硬質の叙述だ。ことさらに供養を拒む「私」はその中心にいる。
作者の透徹した人間への深い眼差しが小説を支えていることをあらためて知らされる。家族という残酷な桎梏を知悉しているからこその、人間への幼稚な期待や不遜な決めつけに流されることなく、もとより葛藤を内包した静謐な眼差しである。